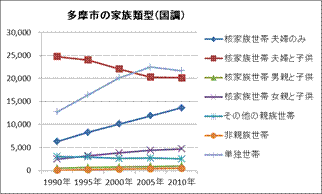友人に何人か独身女性がいるが、定職に付き経済的に余裕がある暮らしの人はマンションを購入しているケースが多いようだ。生涯、独りを貫くつもりは無くても当面が独りならば、安心して住める環境を確保しようとセキュリティのあるマンション住まいを求めるのは当然といえば当然。オートロックのあるマンション住まいが普通になるようだ。男一人の場合はUR賃貸でもいいのだか、女性の場合は、若いうちは民間のセキュリティのある賃貸で、収入が伴ってくるとオートロックの分譲マンションを購入することとなる。
しかし、会社人間を通している間は会社関係の付き合いも含めて単身同士の友人関係が保たれるが、次第に家族の都合で共に行動できなくなると、ふと寂しさも感じるようになる。まあ単身女性だけに限ったことではないのだが、女性の場合はより頻繁に仲間を欲しがるようになるようだ。だから集まって住むという企画には共鳴するところが多い。生物的に群れを離れてボス猿の椅子を狙っているのはオスだし、団地に引きこもるのも男。女は何かと外に出てきて、あれこれと関わりを持つ。だから知人も増えて、無作為の友人も増える。
男尊女卑の教育や社会の中で育ってきたのだから、必然的に女性は誰かに頼ることを是として生きてきた文化がある。親に頼って生きてきて、結婚で亭主に頼って、亭主の親の面倒を診ることまでして忠義を果たして、ようやく亭主を見送ると、今後は子供を頼るようになるという流れ。しかし、男は自立することを強要され、誰かに頼ることを恥ずべきだと教育される。人の上に立つことを是と教おられているから、群れを成しての生活がどこかぎこちない。学生寮や男子寮でも、どこかに上下関係が存在して、それが社会秩序となっていなければ居心地の悪いことになる。
新しい環境に飛び込んできても、「昔の手柄」を口走る。大概決まったパターンが飛び出してきて、出会いの最初に互いに披露しあっているうちは良いのだが、一方的な話になるとコミュニケーションも崩れてしまう。男というのは難儀なもの。やはり男のわがままを受け止める女性がいてこそコミュニティに溶けこむことができるのかもしれない。肩書きを言う男は嫌われることがわかっているのだから、これからは次第に女的に変身した男が現れるかもしれない。リストラで早期退職してガードマンやっている人は、自分の昔を語りたがらないかもしれないし、派遣社員で人生を送った人も同じだろう。
男も女も次第に年齢が高じると共に隔たりも薄くなるが、互いに役割が見えていれば一緒に住むという選択もありかもしれない。男子寮と女子寮が隣り合わせてあるようなもので、その間に共同の食堂やリビングが設えられている住まい。そんな男女共有の住まいができると、入ってくれるかな?
![clip_image002[1] clip_image002[1]](http://machisen.net/blog/anki/Windows-Live-Writer/610853c0317a_27A6/clip_image002%5B1%5D_thumb.gif)
![clip_image004[1] clip_image004[1]](http://machisen.net/blog/anki/Windows-Live-Writer/610853c0317a_27A6/clip_image004%5B1%5D_thumb.gif)
![clip_image006[1] clip_image006[1]](http://machisen.net/blog/anki/Windows-Live-Writer/610853c0317a_27A6/clip_image006%5B1%5D_thumb.gif)
![clip_image008[1] clip_image008[1]](http://machisen.net/blog/anki/Windows-Live-Writer/610853c0317a_27A6/clip_image008%5B1%5D_thumb.gif)